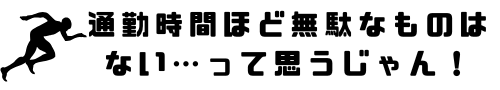やあ、みんな!通勤ネコリーマンだよ。
最近、通勤手当が全額課税になるって噂を聞いて不安になってる人も多いんじゃないかな。ボクも最初は心配したけど、実際のところはどうなのか、しっかり調べてみたんだ。今日はその真相について、わかりやすく解説していくね。
この記事のポイント
・通勤手当の全額課税は2025年8月時点で決定していない
・現在は通勤手段ごとに非課税限度額が設定されている
・公共交通機関なら月15万円まで非課税
・自家用車は通勤距離に応じて月4,200円~31,600円まで非課税
・非課税でも社会保険料の計算対象になる点に注意が必要
通勤手当が全額課税になるって本当?気になる真相を徹底解説

2023年に政府の税制調査会で通勤手当への課税について議論されたことから、インターネット上で「通勤手当が課税対象になる」という噂が広まったんだよね。ボクの周りでも心配している人がたくさんいたよ。
でも安心してほしい。2025年8月現在、通勤手当を全額課税する方針は正式に決まっていないんだ。あくまで「検討段階」であって、実施が確定したわけじゃないんだよ。
確かに税制調査会の答申には「政策的に非課税とされているものを見直す」という文言があるけれど、通勤手当と名指しされているわけでもないし、具体的なスケジュールも示されていないんだ。だから、今のところは従来通りの制度が続くと考えて大丈夫だよ。
そもそも通勤手当って何?交通費との違いも解説
通勤手当というのは、従業員が自宅から会社まで通勤するときにかかる費用を、会社が負担してくれる制度のことなんだ。電車やバスの定期代、自家用車で通勤する人ならガソリン代などが該当するよ。
ここで混同しやすいのが「交通費」との違いだね。交通費は営業先への訪問や出張など、業務のために別の場所へ移動したときにかかる費用を指すんだ。通勤手当は毎日の通勤に使う費用で、交通費は業務上必要な移動の費用という違いがあるよ。
もう一つ大事なポイントは、通勤手当の支給は法律で義務づけられていないということ。つまり、会社が福利厚生の一環として自由に決められるんだよね。だから会社によって支給額や条件が違っているんだ。
現在の通勤手当は非課税限度額内なら税金がかからない

通勤手当には「非課税限度額」というものが設定されているんだ。この金額内であれば所得税がかからない仕組みになっているよ。
公共交通機関を使っている人の場合、月15万円までが非課税になる。これは平成28年の法改正で、以前の10万円から引き上げられたものなんだよね。ただし、わざわざ遠回りしたり、必要もないのに特急やグリーン車を使ったりすると、合理的じゃないと判断されて課税対象になることもあるから注意が必要だよ。
自家用車や自転車で通勤している人は、通勤距離によって非課税限度額が変わってくるんだ。片道2キロメートル未満だと全額課税になっちゃうけど、2キロメートル以上なら距離に応じて月4,200円から31,600円までが非課税になるよ。
交通機関と自家用車を組み合わせて使う場合はどうなる?
最寄り駅まで自家用車で行って、そこから電車に乗るというパターンもあるよね。このように交通機関と自家用車を併用している場合は、それぞれの非課税限度額を合計した金額が、月15万円以内なら非課税になるんだ。
たとえば、電車の定期代が月1万円で、自宅から駅までの距離が片道8キロメートルだとすると、1万円プラス4,200円で合計14,200円。これは15万円を下回っているから全額非課税になるよ。
ただし、この場合も合理的なルートを選んでいることが前提になる。遠回りして高い費用がかかるルートを選ぶと、課税対象になる可能性があるから気をつけようね。
通勤手当の計算方法と知っておきたい注意点
通勤手当がどうやって計算されるのか、よくわからない人も多いんじゃないかな。実は通勤手段によって計算方法が違うから、それぞれ見ていこうね。

電車やバスを使う人の通勤手当計算方法
公共交通機関を利用している人の場合、多くの会社では定期券代を支給しているよ。定期券がない路線なら、片道運賃を2倍して月間の労働日数をかけた金額を支給するのが一般的なんだ。
支給のタイミングは1カ月分ずつというパターンが多いけれど、3カ月定期や6カ月定期を購入している場合は、その期間分をまとめて先払いすることもできるんだよ。実際、長期の定期券のほうが割引率が高いから、まとめて支給したほうがお得になることが多いんだよね。
自家用車通勤の人はどう計算する?
マイカー通勤の人の場合は、1キロメートルあたりのガソリン代を会社が決めて、それに往復の通勤距離と月間労働日数をかけて計算するよ。
具体的には「1キロメートルあたりのガソリン代×往復通勤距離×月間労働日数」という計算式を使うんだ。1キロメートルあたりのガソリン代は会社によって違うけれど、だいたい10円から20円くらいに設定しているところが多いね。
ちなみに駐車場代を会社が負担してくれる場合もあるけど、駐車場代は非課税にならないから注意してほしいんだ。
自転車通勤の計算は会社によって違う
自転車で通勤している人への支給方法は、実は明確なルールがないんだよね。だから会社によって計算方法がバラバラなんだ。
駐輪場費用や保険料、雨の日に別の交通手段を使う必要性なども考えて、定額で支給する会社もあるよ。電車やバスを使う人と同じように定期代相当額を支給したり、通勤距離に応じて独自の計算方法を作っている会社もあるね。
ただし、非課税限度額は自家用車と同じだから、その範囲内で支給されることが多いんだ。自転車の場合も駐輪場費用は課税対象になるから覚えておこうね。
令和7年秋に自家用車通勤の非課税限度額が引き上げられる予定

ここで嬉しいニュースがあるんだ。政府は令和7年の秋をめどに、マイカー通勤者への通勤手当の非課税限度額を引き上げる方針を示しているんだよ。
これが実現すれば、平成28年から11年ぶりの引き上げになる。背景には最近のガソリン価格の高騰があって、マイカー通勤の人の負担が増えているからなんだよね。
報道によると、距離区分ごとに数百円から2,000円程度が上積みされる案が検討されているらしいよ。課税対象だった部分が非課税になれば、所得税や住民税の負担が減って手取りが増えるから、マイカー通勤の人にとっては朗報だね。
通勤手当を支給するときの注意点を押さえよう
会社が通勤手当を支給する場合、就業規則にしっかりと要件を書いておく必要があるんだ。どんな通勤手段の人が対象なのか、支給額の計算方法はどうするのか、上限額はいくらなのかといった内容を明記しておかないといけないよ。
それから大事なポイントとして、雇用形態によって支給額に差をつけることは認められていないんだ。正社員だけじゃなく、アルバイトやパートの人にも同じように適切な金額を支給する必要があるよ。
社会保険料の計算では通勤手当も含まれる点に要注意
ここがちょっとややこしいところなんだけど、所得税では非課税になる通勤手当も、社会保険料を計算するときには含めないといけないんだ。
社会保険料は基本給だけじゃなくて、通勤手当などの各種手当を全部含めた月額報酬をもとに計算される。だから、非課税だからといって計算から外しちゃうと間違いになるから気をつけようね。
また、通勤手当を含めた年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れることになる。給与だけじゃなく手当の額も正確に把握しておくことが大切なんだよ。
テレワーク勤務の人の通勤手当はどう扱う?
最近はテレワークを導入している会社も増えているよね。在宅勤務が多い従業員の場合、毎日出社するわけじゃないから定期券を買うのはもったいないことになるんだ。
そういう場合は、実際に出勤した日数に応じて実費分を計算して支給するのがいいだろうね。出勤日だけの交通費を「交通費」として精算すれば、通勤手当としてカウントしない対応も可能だよ。
取引先に直行してそのまま帰宅するケースなんかも、通勤手当じゃなくて交通費として扱えば柔軟に対応できるんだ。
通勤手当が全額課税になる?まとめ
今回は通勤手当の課税について、詳しく見てきたよ。繰り返しになるけど、2025年8月時点では通勤手当の全額課税は決定していないから安心してね。今後の動向には注意が必要だけど、今すぐ慌てる必要はないんだ。
記事の要点まとめ
・通勤手当の全額課税は検討段階で正式決定していない
・公共交通機関利用者は月15万円まで非課税
・自家用車通勤者は距離に応じて月4,200円~31,600円が非課税
・令和7年秋に自家用車通勤の非課税限度額引き上げ予定
・交通機関と自家用車併用なら合計15万円まで非課税
・所得税は非課税でも社会保険料の計算対象になる
・テレワーク勤務者は実費精算がおすすめ
・雇用形態による支給額の差別は認められない
通勤手当の制度は複雑に感じるかもしれないけど、基本を理解しておけば大丈夫。ボクたち働く側にとって大切な制度だから、正しい知識を持っておこうね。
それじゃあ、また次の記事で会おう!